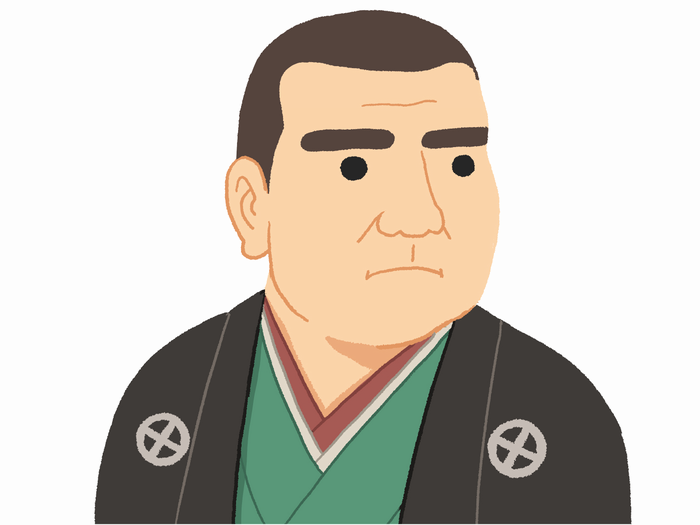豊臣秀吉がした5つのこと

天下統一を完成させた
豊臣秀吉は、もともと織田信長の家来でした。信長は「天下統一」を目指して各地を攻めていましたが、1582年、「本能寺の変」で家来の明智光秀に裏切られて命を落とします。
信長の死後、秀吉はすぐに動き、山崎の戦いで光秀を討ち取りました。
これによって、信長の後継ぎ争いに勝ち、力を強めていきます。
その後、各地の大名を次々に従わせ、1585年に関白となり、1590年には小田原を中心とする北条氏を滅ぼして、「天下統一」を成し遂げました。
太閤検地を行った

秀吉は、国をしっかり治めるために「太閤検地(たいこうけんち)」を行いました。
「検地」とは、田んぼや畑の広さや、そこからとれるお米の量を正しく調べることです。
それまで土地の広さや持ち主はあいまいだったため、不公平なことが多く起きていました。秀吉は全国の土地を調べて、「誰が」「どれくらいの田んぼを持っているか」を記録し、年貢=税金として納めるお米の量をはっきり決めたのです。
この検地によって、農民は土地にしっかりしがみつくことができ、大名も安心して国を治められるようになりました。
太閤検地では、「石高(こくだか)」という単位が使われます。
1石(こく)はお米が約150kg、だいたい人が1年間食べる量にあたります。
この「石高」によって、領地の力(経済力)が数字で示されるようになりました。太閤検地は、江戸時代のしくみのもとにもなった、とても重要な改革です。
刀狩を行った
豊臣秀吉は、1590年ごろから「刀狩(かたながり)」という政策を進めました。
これは、農民たちが持っていた刀や弓、槍(やり)などの武器を集めて取り上げることです。
なぜこんなことをしたのでしょうか?
それは、農民たちが反乱を起こすのを防ぐためです。当時の日本では、農民の中にも武器を持っている人が多く、時には反乱を起こして国を乱すことがありました。
秀吉は、「武士」と「農民」の区別をはっきりさせ、農民は田んぼを作ることに専念させるために刀狩を行ったのです。
集めた武器は、奈良の大仏殿(だいぶつでん)を作る材料にした、とも言われています。
これによって、国は平和に近づき、農業も安定しました。
刀狩は、武士と農民をはっきり区別する「身分制度」のスタートでもあり、のちの江戸時代の社会づくりにもつながっていきます。
朝鮮出兵をした
豊臣秀吉は、日本だけでは満足せず、海外にも目を向けました。
1592年、朝鮮半島に大軍を送る「朝鮮出兵(ちょうせんしゅっぺい)」を始めます。
中国の明(みん)を征服しようと考え、その通り道である朝鮮を攻めたのです。
この戦いは「文禄(ぶんろく)の役」と呼ばれます。
最初は日本軍が優勢でしたが、やがて朝鮮軍や明の援軍の反撃にあい、思うように進みませんでした。
一時休戦したものの、1597年にはふたたび戦いが始まります(「慶長(けいちょう)の役」)。
しかし、秀吉が1598年に亡くなると、日本軍はすぐに引き上げました。
朝鮮出兵は、日本にとっても多くの犠牲を出し、国の力を消耗させた戦いでした。
大阪城を築いた

豊臣秀吉は、自分の権力を全国に示すために、大きくて立派な城を築きました。
それが「大阪城」です。
1583年ごろから建設が始まり、当時としてはとても大きく、豪華な城でした。大阪城は、周りを堀(ほり)と高い石垣(いしがき)でかため、敵が簡単には攻め落とせないように作られていました。
また、天守閣とよばれる高い建物もあり、金箔を使ったきらびやかな装飾もほどこされました。
この大阪城は、ただの城ではありません。秀吉が「天下を取ったぞ!」ということを日本中にアピールするための象徴でもあったのです。
のちに徳川家康との「大坂の陣」で大阪城は攻め落とされ、豊臣家は滅亡しますが、大阪城は今も観光名所として多くの人に親しまれています。
AI豊臣秀吉が小学生の質問に答える!

AIが豊臣秀吉になり切って小学生からの質問に答えます。
関白ってどんな仕事だったの?どうしてなれたの?

AI秀吉
関白とは、天皇さまの代わりに政治をする偉い役目じゃ。もとは貴族がなるものじゃったが、わしの力と知恵を認められて、特別にならせてもらったんじゃ。百姓あがりでは前代未聞じゃぞ!
「刀狩り」ってなんのためにしたの?

AI秀吉
うむ、刀狩りは、百姓が武器を持って反乱を起こさぬようにするためじゃ。戦が終わったら、武器はいらん。みなが農業に専念できるよう、安心して暮らせるようにしたかったんじゃよ。
朝鮮に戦いに行ったのはなぜ?日本だけじゃダメだったの?

AI秀吉
ふふふ、わしはもっと大きな夢を持っておった。中国(明)を手に入れて、大きな国を作りたかったんじゃ。そのために朝鮮を通って攻めようとしたのじゃが……思ったより手ごわかったのう。
戦った相手で一番強かったのは誰?

AI秀吉
柴田勝家(しばた かついえ)。
こやつが、わしにとって最初にして最大の強敵じゃった!
天正11年(1583年)の「賤ヶ岳(しずがたけ)の戦い」では、信長さまの死後、後継ぎ争いでわしと勝家がぶつかった。
勝家は経験豊富な武将で、戦いぶりも豪胆そのもの。兵も多く、わしにとっては大ピンチじゃったが……そこでわしの家臣・福島正則や加藤清正らが大活躍し、「賤ヶ岳の七本槍」として名をあげたんじゃ。
わしはすばやく軍を動かして勝家を破った。
あれはまさに、「知恵」と「スピード」で勝った戦じゃな。
信長がこわくなかったの?

AI秀吉
めちゃくちゃ、こわかったぞ!あの方はな、目がすわっていて、機嫌が悪いと家臣をバッサリ切ることもあった。下っ端のころは、そりゃもう、ピリピリじゃ。
でもな、信長さまは「できる者はどんどん出世させる」お方じゃ。わしのような身分の低い者にもチャンスをくださった。それが、うれしかったんじゃよ。
こわかったけれど、心の底から尊敬しておった。
わしが天下を取れたのも、信長さまのそばで学べたからじゃ。
信長さまが本能寺で倒れたとき、わしは心の中でこう叫んだんじゃ。
「信長さま、ここからはわしがやりまする!」とな。
信長さまはこわいけど、すごい人。わしはその背中を見て育ったんじゃ。怒られても、がんばる気持ちを忘れなかった。それが、わしの出世のもとじゃよ!
徳川家康のことをどう思う?

AI秀吉
おお、またもや気になるところを聞いてくるのう!
―「徳川家康のことをどう思うか?」じゃと?それはのう……
ずばり、「油断ならぬキツネのような男」じゃ。見た目はおだやかで、のんびりしているように見えるが、心の中では常に計算し、じっとチャンスをうかがっておる。
しかも、我慢強い。わしがイライラしておるころでも、家康は笑って何も言わん。だが、それがこわいんじゃ……。
わしが生きておるうちは、重く用いておった。天下統一のためには、家康の力も必要じゃったからのう。「お主は東国(関東)をまかせる」と言って、立派な城も与えておったんじゃ。
じゃが……わしが死んだあと、やはり動いたのう。息子・秀頼の代で、家康はとうとう「将軍」になり、豊臣を押しのけて天下を取ったんじゃ。
正直に言えば――「うまくやりおったな、家康め!」「じゃが、わしのような派手さはなかったのう!」じゃ。
わしは金ぴかの城に、天下統一の夢!
家康は地味にコツコツ、でも最後はしっかり勝ち残る。そんな男よ。
いま日本では、お米が高くなって困っているんですが、秀吉さんならどうしますか?

AI秀吉
おお、それはなかなかの難題じゃのう……。米が高くて人々が困っておるとな!?――ならば、わし、豊臣秀吉が出てまいろう!
まずは全国の米の収穫と在庫をしっかり調べる。
これはわしがやった「太閤検地(たいこうけんち)」の出番じゃ!
誰の土地に、どれだけ米がとれて、どこに保管されているか――。
それを正しく知ることが、まず第一じゃ!
米だけが食べ物ではない。
わしは「芋」「麦」「雑穀」なども育てるように命じるじゃろう。
食べものの選択肢を広げて、みんなが食べられるようにするんじゃ!
米の値段が急に上がったり下がったりすると、民は困る。
わしは「米座(こめざ)」をつくって、値段が安定するしくみを考えるぞい。
市場にまかせきりではあかん。
天下人の目が届いてこそ、民は安心して暮らせるのじゃ!
わしが農民出身だからこそ、
「食えぬつらさ」は骨身にしみてわかっておる!
民が腹をすかせて笑えぬ国に、天下の価値はない。
だからこそ、わしは民が飢えぬように、手を尽くすのじゃ!
「米が高けりゃ、知恵で下げよ!」
「民の暮らしを守るのが、天下人のつとめじゃ!」
わしなら――まず米を調べ、かくす者をただし、みんなが食える世にしてみせる!それが豊臣秀吉という男よ!
豊臣秀吉の調べ学習ヒント
豊臣秀吉の年表
| 1537年 | 尾張国(今の愛知県)の貧しい家に生まれる(幼名:日吉丸) |
|---|---|
| 1560年頃 | 織田信長につかえる。足軽(あしがる)からスタート |
| 1566年 | 墨俣城を一夜で築く |
| 1570年 | 姉川の戦い |
| 1582年 | 本能寺の変、山崎の戦いで明智光秀を破る |
| 1583年 | 賤ヶ岳(しずがたけ)の戦いで柴田勝家に勝利 |
| 1584年 | 小牧・長久手の戦いで徳川家康と戦う |
| 1585年 | 関白(かんぱく)になる |
| 1586年 | 太政大臣(だいじょうだいじん)に就任、「豊臣」姓をもらう |
| 1590年 | 小田原攻めで北条氏を滅ぼし、天下統一を完成させる |
| 1592年 | 文禄の役(最初の朝鮮出兵)を始める |
| 1597年 | 慶長の役(2度目の朝鮮出兵)を始める |
| 1598年 | 死去(享年62歳) |
豊臣秀吉の有名なエピソード
若いころ、秀吉は織田信長に仕える下働き「草履取り」をしていました。ある寒い日、秀吉は信長が外出する前に、草履をふところで温めておいたと言われています。
冷たい草履をはかずにすんだ信長は大よろこびし、秀吉の細かい気くばりを高く評価したそうです。
「墨俣一夜城(すのまたいちやじょう)」と呼ばれる伝説があります。信長の命令で、敵の近くに急いで城を作る必要がありました。秀吉は、川を利用してあらかじめ作った木のパーツを組み立てる方法を考え、一晩で城を完成させたように見せかけたのです。
豊臣秀吉と関連する人物一覧表
| 人物名 | 立場・関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 織田信長 | 主君 | 秀吉は信長に仕えて力をつけた。信長の死後、天下を目指す。 |
| 明智光秀 | 敵 | 信長を本能寺で討った(ほんのうじのへん)。秀吉が山崎の戦いで光秀をたおす。 |
| 徳川家康 | 同盟者/敵 | 秀吉のもとでは仲間だったが、秀吉の死後に豊臣家とたたかう(関ヶ原の戦い)。 |
| 石田三成 | 家臣 | 秀吉の家来で、まじめに国の仕事をした。秀吉の死後、家康と対立。 |
| 千利休 | 茶道の師 | 茶の湯(茶道)を教え、文化を広めた。のちに秀吉と対立してしまう。 |
| 北政所 | 正室 | 秀吉の妻。秀吉をささえた。ねね、という名前でも知られる。 |
| 淀殿 | 側室 | 秀吉の子・秀頼(ひでより)を産んだ女性。大阪の陣で豊臣家をまもろうとした。 |
| 豊臣秀頼 | 秀吉の子 | 秀吉のあとをつぐが、大坂の陣で徳川家康に敗れる。 |
正室とは正式な妻(本妻)のこと。側室とは本妻以外の妻のこと
関連するキーワード一覧
| キーワード | 内容 | 詳細解説 |
|---|---|---|
| 天下統一 | 全国を一つにまとめること | 秀吉は日本をほぼ統一し、戦国時代を終わらせた。 |
| 本能寺の変 | 織田信長が殺された事件 | このあと、秀吉が光秀をたおして力をのばした。 |
| 山崎の戦い | 秀吉と光秀の戦い | 秀吉が勝って、信長の後継者(こうけいしゃ)争いに勝った。 |
| 太閤検地 | 土地の広さを調べたこと | 全国の田んぼや土地を調べて、税金を正しく集めた。 |
| 刀狩 | 武器をとりあげる政策 | 百姓(農民)が戦えないようにして、平和を守ろうとした。 |
| 朝鮮出兵 | 朝鮮(今の韓国)への遠征 | 大きな戦いを海外で行ったが、失敗に終わった。 |
| 大阪城 | 秀吉が建てた巨大な城 | 天下統一のシンボルとして、立派なお城を作った。 |
| 金の茶室 | 金ぴかの茶室 | 秀吉の力と富をアピールするために作られた。 |
| 関白 | 天皇を助ける最高の役職 | 武士から関白になった珍しい存在。 |
| 太閤 | 関白をやめた後の呼び名 | 「太閤(たいこう)さん」と呼ばれ、親しまれた。 |