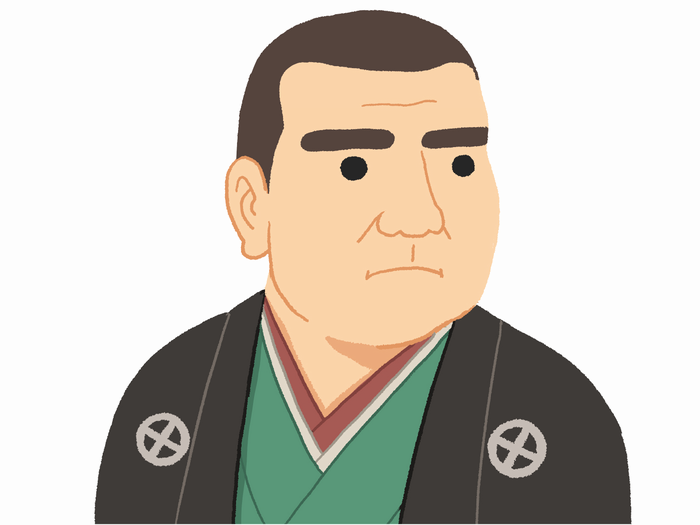中大兄皇子ってどんな人?

未来の天皇、中大兄皇子の正体!
中大兄皇子(なかのおおえのおうじ)は、昔の日本を大きく変えた「日本の大改革リーダー」です。
飛鳥時代の皇族で、のちに「天智天皇(てんじてんのう)」となりました。
この時代、日本はまだ国のしくみがしっかりしていなくて、力をもった豪族(ごうぞく)たちが好き勝手していたんだ。そんな中、国をまとめて強くするために立ち上がったのが中大兄皇子です。
彼は仲間の中臣鎌足(なかとみのかまたり)といっしょに、大きな改革を始めました。
中大兄皇子が活躍した時代
中大兄皇子が活躍した飛鳥時代の中ごろ、日本では「蘇我氏(そがし)」という有力な一族が強い力を持っていました。
もともと天皇を助ける立場だったのに、自分たちの思いどおりに政治を動かし、天皇よりも力があるような状態になっていたのです。そのころ、日本には中国(当時の「唐(とう)」)や朝鮮の進んだ文化や政治のしくみが伝わってきていました。
中大兄皇子は、こうした新しい知識をもとに、日本でも天皇中心の国づくりをめざそうと考えます。
そこで、中大兄皇子は、中臣鎌足と協力し、ついに645年に蘇我氏をたおします。
これが「大化の改新(たいかのかいしん)」のはじまりです。中国の制度を手本にして、土地や人々を国のものとするしくみ(公地公民)など、大きな改革を行いました。
この時代、日本はまだ小さな豪族たちがそれぞれの土地を支配していましたが、中大兄皇子はそれをまとめて、天皇の力を強くする国づくりを進めたのです。
これが、のちの「律令国家」へとつながっていきます。
大化の改新と乙巳の変(いっしのへん)
中大兄皇子と中臣鎌足が645年に宮中で蘇我入鹿(そがのいるか)をたおしました。
これが「乙巳の変(いっしのへん)」とよばれる事件です。
中大兄皇子たちは蘇我氏をたおしたあと、新しい国づくりを始めます。
これが「大化の改新」です。
つまり、「乙巳の変」は改革のきっかけになった事件で、「大化の改新」はそのあとに行われた政治の大改革のことです。
中大兄皇子がしたこと5つにまとめてみた
蘇我氏をたおして政治をあらためた!
当時の日本では、「蘇我入鹿(そがのいるか)」という豪族が、とても強い力を持っていた。
でも、力がありすぎて天皇よりも偉そうにしていたんだ。これはさすがにまずい!
そこで中大兄皇子と中臣鎌足は、「これは国をよくするために必要だ」と決意して、蘇我入鹿をたおした。この事件を「乙巳の変」とよびます。
これが日本の政治を変える第一歩!「天皇中心の国」を作るためのスタートでした。
大化の改新を行った!
蘇我氏をたおしたあとは、「大化の改新(たいかのかいしん)」という大改革を始めます。
当時、土地や人は豪族のものだったけど、それでは国がバラバラのまま。そこで中大兄皇子は、「土地も人も天皇のものにする」=「公地公民(こうちこうみん)」というしくみをつくりました。
これで「天皇を中心とした国づくり」が少しずつ形になっていくんだよ。
改革ってカンタンじゃないけど、やらないと国は変わらない。その勇気と行動力がすごい!
戸籍や税のしくみを作った!
国をまとめるには、「誰がどこに住んでいて、どれくらいの土地をもっているか」をちゃんと記録する必要があります。
そこで中大兄皇子たちは「戸籍(こせき)」を作り、人々の名前や家族、土地のことを記録するしくみをスタート。
それに合わせて、税金をきちんと集める「班田収授法(はんでんしゅうじゅほう)」という制度も考案。これがあるおかげで、国はお金を集めて道や建物を作れるようになりました。
中国のやり方を学んで取り入れた!
当時の中国(唐:とう)は、アジアでいちばん発展していた国。中大兄皇子は、「日本もこんな国になりたい!」と考えて、遣唐使という使いの人たちを中国に送って、いろいろ学んだんだ。
学んだのは政治のやり方だけじゃない。仏教や法律、衣服や文化など、いろんなことを取り入れて、日本の国づくりに生かしたよ。
「いいと思ったものは、どんどん学ぶ」。
それも、国を変える大事な力だったんだね。
天智天皇として新しい都をつくった!
中大兄皇子は、のちに「天智天皇(てんじてんのう)」となって、国づくりを進めました。
そのときに作ったのが「近江大津宮(おうみのおおつのみや)」という新しい都(みやこ)。
今でいう滋賀県の大津市にあたる場所だね。
ここを政治の中心にして、国のルールやしくみを整えたりと改革を続けました。天智天皇の時代は、のちの「律令国家(りつりょうこっか)」へとつながっていく大事な時期となりました。