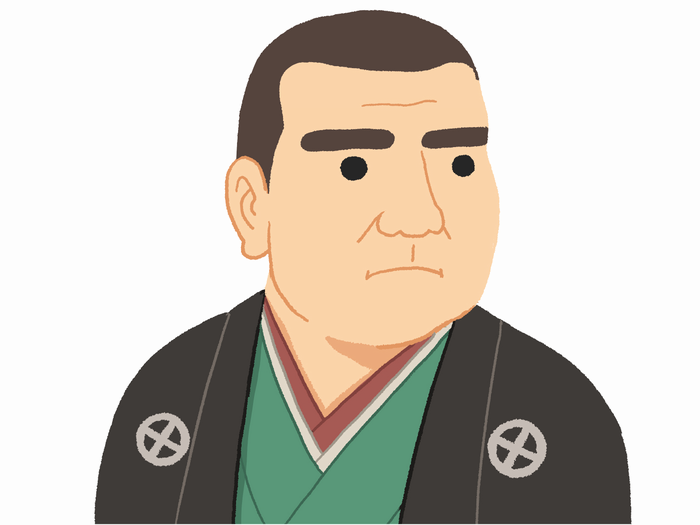徳川家康って何をした人?

1.関ヶ原の戦いで勝って天下を取った
1600年、徳川家康は「関ヶ原の戦い」で、石田三成を中心とした西軍と戦いました。
この戦いは日本全国の大名たちが東軍と西軍に分かれて戦った、まさに「天下分け目の戦い」と呼ばれるほどの大きな戦いです。戦いは1日で終わり、家康の東軍が大勝利!
家康はこの戦いに勝利したことで実質的に日本の支配者となりました。
関ヶ原の戦いは、家康が天下を取るための決定的な出来事だったのです。
2.江戸幕府をひらいた
関ヶ原の戦いに勝利した徳川家康は、1603年に朝廷から「征夷大将軍(せいいたいしょうぐん)」に任命され、江戸に幕府を開きました。
「征夷大将軍」とは、武士のリーダーとして国を治める役職です。これが「江戸幕府」の始まりで、日本の中心が京都や大阪から江戸(現在の東京)に移ることになりました。
江戸幕府は約260年間続く長い時代、「江戸時代」のスタートとなります。
家康は、幕府の仕組みをしっかり整え、将軍が政治を行う仕組みを作りました。
家康の目標は、戦のない安定した国を作ることだったため、全国の大名たちが勝手に行動できないようにし、強い中央の力で国全体をまとめようとしたのです。
3. 平和な時代をつくるしくみを作った
戦国時代は、何十年もの間、日本中で戦いが続いていた乱れた時代でした。しかし、徳川家康が江戸幕府を開いたあと、日本は約260年間もの間、戦争のない平和な時代に入りました。
家康は戦を防ぐため、大名同士が戦わないようにする制度を作り、政治の安定を保ちました。
また、農業を重視し、人々がしっかり暮らせるように税の仕組みを整えました。
町や村も発展し、教育や文化も栄えました。このようにして、家康が作った政治のしくみが、長い平和をもたらしたのです。人々が安心して暮らせる時代をつくった家康の功績は、日本の歴史の中でもとても大きなものだといえます。
4. 大名をコントロールする仕組みを作った
徳川家康は、戦国時代のように大名たちが自由に戦争を始めないように、さまざまなルールを作りました。そのひとつが「武家諸法度(ぶけしょはっと)」です。
これは大名たちの行動を制限する法律で、幕府の許可なしに結婚したり、大きな城を建てたりすることができなくなりました。
また、「参勤交代(さんきんこうたい)」という制度も重要です。これは、大名が1年おきに自分の領地と江戸を行き来しなければならない制度で、江戸での生活費がかかるため、戦の準備ができないようにしたのです。
さらに、大名の家族を江戸に住まわせることで、人質のようにして反乱を防ぎました。これらの制度によって、大名たちは幕府に逆らうことができなくなり、平和が保たれました。
5. 経済を発展させた
徳川家康は、日本の経済を安定させるためにも多くの取り組みをしました。
まず、全国で同じように使える「貨幣制度(かへいせいど)」を整えました。金や銀、銅などで作られたお金を使うことで、物の売り買いがしやすくなり、商人たちの活動が活発になりました。
また、街道を整備して、人や物が行き来しやすくしました。とくに「東海道(とうかいどう)」などの道は、江戸と各地をつなぎ、商売や旅にとても役立ちました。
さらに、市や町も発展し、商人や職人たちが活躍するようになりました。こうした家康の経済政策により、江戸時代には経済が大きく成長し、人々の暮らしも豊かになっていったのです。
AI徳川家康に聞いてみた

AIに徳川家康になってもらい、小学生からの質問に答えてもらいました。

AI家康
よし、わしは徳川家康じゃ。なんでも聞いてみるがよいぞ。
どうして江戸に幕府を開いたの?

AI家康
うむ、良いところに気づいたのう。
京都は古くからの都で、天皇さまもおられる大事な場所じゃ。
じゃが、わしが江戸を選んだのには理由がある。
江戸は当時まだ田舎じゃったが、海にも川にも近くて、物のやりとりがしやすい場所だった。また、まわりを山や海で囲まれて、守りもしやすかったのじゃ。
それに、京や大坂からは少し離れておるから、まわりに気をつかいすぎず、自分の思い通りに政治をしやすかった。
将来の発展を見すえて、あえて江戸を選んだのじゃよ。
戦った相手の中で一番強かった武将は?

AI家康
わしが戦った相手の中で「一番強かった武将」と申すなら、
武田信玄(たけだ しんげん)。この男こそ、もっとも手ごわかった相手じゃ
信玄は、戦の天才じゃった。戦いの形(陣形)を自在にあやつり、「風林火山」の旗のごとく、速くて力強く、まるで大自然のごとき軍じゃった。
わしが一度、三方ヶ原(みかたがはら)というところで戦ったときなど、まるで歯が立たず、ボロボロに負けたのじゃ…。
そのとき、わしは命からがら城へにげ帰り、敗戦の自画像まで描かせたほどじゃ。実際に「しかみ像」というものが残っておる。恥をしのんで教訓にしたのじゃ
しかしのう、信玄どのが病に倒れなければ、
わしは天下を取れなんだかもしれぬ…それほどにおそろしい男じゃった。
織田信長と豊臣秀吉のことをどう思ってたの?

AI家康
信長公は、まさしく「革命の人」じゃ。古いしきたりを打ちこわし、新しい時代をつくろうとした。その勢いと知恵は天才的じゃった。
わしは若いころから信長公と手を組み、何度も共に戦をした。ときには意見が合わぬこともあったが、「この男が天下を変えるかもしれぬ」と思っておった。
ただのう……信長公は人をおそれぬ分、敵も多かった。あの本能寺の変も、まさに「強すぎるゆえに倒れた」――そういう最期じゃったと思うのう。
秀吉どのは、わしにとっては「すごいけど、こわい男」じゃった。
百姓(ひゃくしょう)出身から天下人にのぼりつめるという、まれなる努力の人。頭も切れるし、気配りもすごい。あっぱれというしかない。
しかし、わしはその頭の回転の早さゆえに、いつ自分が追い落とされるか分からぬ…と、ずっと気をはっておったのじゃ。
(実際、わしの家臣の一部は秀吉どのに取りこまれておったからのう…)
じゃが、秀吉どのが亡くなったあとは、わしがその遺志を受け継ぎ、
天下を安定させたつもりじゃ。
江戸幕府が滅ぶとしたら、どんな理由だと思う?

AI家康
わしが思うに、江戸幕府が滅ぶとしたら、その理由はおそらく三つある。
武士はもともと戦うためにおる。ところが平和が長く続くと、「戦わぬ武士」ばかりになる。
そうなると、国を守るはずの者たちが、ただの役人やお金もちになるのじゃ。民の信頼も失われていくじゃろう。
もしも外国の力が大きくなって、船や大砲でせめてくるようになったら――鎖国をして、外の国と交流を断っていたわしらの国は、すぐに困るじゃろう。
知識も、武器も、話し合いもできぬまま、負けるかもしれん。
民が苦しんでおるのに、お上(幕府)だけがぜいたくをしていたら、いつかきっと、民は怒るじゃろう。一揆(いっき)や反乱がおこり、国がまとまらなくなる。
「民を大事にせよ」とわしは言い残したが、それを忘れれば…幕府は終わる。
どうすれば勉強が出来るようになりますか?

AI家康
わしも若いころは、兵法書(へいほうしょ)を読んでもすぐ眠くなっておったぞ…。じゃが、勉強が苦手でも、工夫しだいで変われるのじゃ
わしがまずしたのは、「わかるところだけ読む」ことじゃ。
むずかしいことを最初にすると、心が折れてしまうからのう。ちょっとでも「おもしろい」と思えるところを広げていけば、だんだん前に進めるぞ。
わしは「鳴かぬなら 鳴くまで待とう ホトトギス」と申した。
これは、「すぐできなくても、あせらず待て」という意味じゃ。
勉強も、1日10分でもよい。毎日コツコツやれば、力はついていく。
わしは、学んだことを家臣に話して聞かせておった。人に教えると、記憶がグッと深まるのじゃ。
家の人、友だち、ノートに向かってでもよい。「教えるつもりで学ぶ」と、どんどんわかるようになるぞ。
秀吉どのも、最初は下っ端の足軽じゃった。だれでも最初は「できない」から始まる。昨日の自分よりちょっと進んだなら、それでじゅうぶん立派じゃ!
徳川家康の調べ学習向け資料
徳川家康の年表
| 1543年 | 三河(今の愛知県)に生まれる。名前は「竹千代」。 |
|---|---|
| 1547年 | 今川家の人質としてくらしはじめる。 |
| 1560年 | 今川義元が「桶狭間の戦い」で戦死。家康が独立しはじめる。 |
| 1562年 | 織田信長と「清洲同盟」を結び、協力する。 |
| 1575年 | 「長篠の戦い」で信長といっしょに武田軍をたおす。 |
| 1582年 | 本能寺の変で信長が死ぬ。家康は三河へ逃げて命を守る。 |
| 1584年 | 「小牧・長久手の戦い」で豊臣秀吉と戦うが決着つかず。 |
| 1590年 | 豊臣秀吉に命じられて、関東に移り、「江戸」に入る。 |
| 1600年 | 「関ヶ原の戦い」で勝ち、日本のトップに近づく。 |
| 1603年 | 「征夷大将軍」になり、江戸幕府をひらく。 |
| 1605年 | 将軍を子ども(徳川秀忠)にゆずるが、影で政治を続ける。 |
| 1615年 | 「大阪夏の陣」で豊臣家をほろぼす。戦国時代が終わる。 |
| 1616年 | 死去。「日光東照宮」にまつられる。 |
徳川家康と関係のある人物一覧表
| 人物 | よみ | 人物像 | 家康との関係 |
|---|---|---|---|
| 今川義元 | いまがわ よしもと | 駿河の大名。桶狭間の戦いで戦死。 | 少年時代、家康は今川家の人質だった。 |
| 織田信長 | おだ のぶなが | 天下統一前に本能寺の変で死ぬ。 | 家康と同盟をむすび、いっしょに戦った。 |
| 豊臣秀吉 | とよとみ ひでよし | 信長のあとに天下を統一。 | 家康を関東へうつした。 |
| 徳川秀忠 | とくがわ ひでただ | 家康の息子で、2代目将軍。 | 家康から将軍の地位をゆずられた。 |
| 徳川家光 | とくがわ いえみつ | 家康の孫で、3代目将軍。 | 家康の政治を受けつぎ、幕府を安定させた。 |
| 石田三成 | いしだ みつなり | 豊臣家の家来で政治が得意。 | 関ヶ原の戦いで家康と戦い、敗れる。 |
| 本多忠勝 | ほんだ ただかつ | 家康の家来で、とても強い武将。 | 家康の右うでとして、たくさんの戦いに出た。 |
| 井伊直政 | いい なおまさ | 家康の家来。 | 家康の東軍の中でも中心の力をもった。 |
| 真田幸村 | さなだ ゆきむら | 大坂の陣で活やくした武将。 | 家康の大きな敵の一人だった。 |
何問わかる?徳川家康クイズ
| 問題 | ヒント | 正解 |
|---|---|---|
| 徳川家康は何県に生まれた? | 昔の「三河の国」 | 愛知県 |
| 家康の子どものころの名前は? | ○○千代という名前 | 竹千代 |
| 家康を人質にしていた大名はだれ? | 桶狭間で負けた人 | 今川義元 |
| 家康が結んだ信長との同盟は? | 地名がついてる | 清洲同盟 |
| 家康が勝った大きな戦い(1600年)は? | 日本を二つに分けた戦い | 関ヶ原の戦い |
| 江戸幕府をひらいた年は? | 関ヶ原の3年後 | 1603年 |
| 家康が幕府をひらいた都市は? | 今の東京 | 江戸 |
| 家康が倒した豊臣家の最後の戦いは? | 夏と冬がある戦い | 大坂の陣 |
| 家康が死んでまつられた神社は? | 栃木県にある | 日光東照宮 |
| 家康の家来で「無敵」といわれた武将は? | 一度も負けなかった | 本多忠勝 |
| 家康が戦った「赤いよろい」の軍を持つ家来は? | ○○直政 | 井伊直政 |
| 家康の孫で3代将軍になったのは? | 「光」の字が入る | 徳川家光 |
| 家康と戦った豊臣の武将で「六文銭」で有名なのは? | 「真田丸」も人気 | 真田幸村 |
| 江戸幕府は何代つづいた? | 約260年つづいた | 15代 |
| 家康のことを神様としてまつった名前は? | ○照○○○ | 東照大権現 |
| 「鳴かぬなら…」の家康バージョンは? | 辛抱づよい性格 | 鳴くまで待とうホトトギス |
| 家康が最初に住んでいたお城は? | 愛知県にある | 岡崎城 |
| 家康が江戸に来たのは何年? | 秀吉に命じられた | 1590年 |