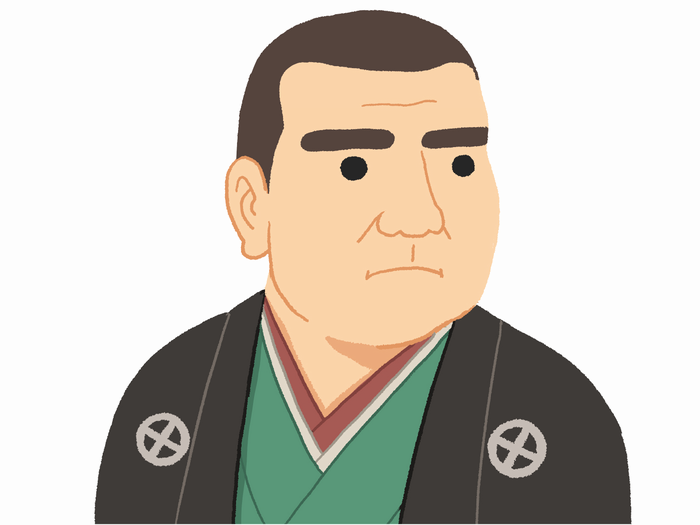聖武天皇がしたこと10選。いくつ知ってる?

奈良の大仏を作った!
奈良の大仏は聖武天皇が作るよう命じたものです。高さは約15メートル、重さは250トン以上!
みんなの幸せと平和を願って、全国の人たちの協力で完成しました。
東大寺を建てた!
奈良の大仏があるお寺、それが東大寺(とうだいじ)です。
大仏をまつるために作られたお寺で、今でも多くの人が訪れる名所になっています。
この東大寺も、聖武天皇の時代に建てられました。
国ごとに「国分寺・国分尼寺」を作った!
聖武天皇は、「全国にお寺を作ろう!」と考えました。
それが「国分寺(こくぶんじ)」と「国分尼寺(こくぶんにじ)」。
各地に同じようなお寺を作って、仏教の力で国を守ろうとしました。
正倉院を作った!
「正倉院(しょうそういん)」って聞いたことありますか?
これは、聖武天皇の宝物をしまっておく「お宝の倉庫」!
当時の貴重な品が、今でも残っていて、奈良時代のくらしを知る手がかりになっています。
戸籍をつくった!
今の日本でも使われている「戸籍(こせき)」のもとになるしくみを作ったのも、聖武天皇。
人びとの名前や年れい、住んでいる場所などを記録して、税や労働の管理に使っていました。
光明皇后と力を合わせた!
聖武天皇の奥さん、光明皇后(こうみょうこうごう)は、病気の人を助ける施設を作ったことで有名。
ふたりは力を合わせて、人びとのために動いた「思いやりコンビ」でした。
お経を集めて広めた!
仏教の教えを大切にしていた聖武天皇は、お経(仏教の教えが書かれた本)を全国に広めました。
「仏教で心をひとつにして、平和な国にしよう」と考えました。
天平文化が花開いた!
聖武天皇の時代は、「天平文化(てんぴょうぶんか)」と呼ばれる、すばらしい文化が広まりました。
仏像、建築、絵画、音楽など、外国の文化と日本の文化がまじりあった、豪華な時代でした。
災いをおさめるために仏教を大事にした!
天災(地震やききん)が続いたとき、聖武天皇は「仏教の力で国を守りたい」と考えました。
それが、大仏づくりやお寺づくりの大きな理由のひとつでした。
平和な国づくりを目指した!
聖武天皇の「国づくり」は、戦いではなく心のしあわせと平和が目標。
「仏教を信じ、国と人がともにしあわせになること」を本気で考えた、すごいリーダーでした。
聖武天皇に関する基礎知識
聖武天皇の関連年表
| 701年 | 聖武天皇が生まれる(お名前は首(おびと)王)。 |
|---|---|
| 724年 | 聖武天皇が即位(天皇になる)。 |
| 728年 | 皇太子(第一子・基王)が亡くなる。 |
| 740年 | 藤原広嗣(ふじわらのひろつぐ)の乱が起きる(九州での反乱)。 |
| 741年 | 国ごとに「国分寺・国分尼寺」を作るよう命じる。 |
| 743年 | 「大仏造立の詔(だいぶつぞうりゅうのみことのり)」を出し、大仏づくりを始めることを発表。 |
| 745年 | 東大寺の大仏の場所を現在の奈良に決める。 |
| 749年 | 聖武天皇が位をゆずり、娘の孝謙天皇(こうけんてんのう)が即位。聖武天皇は「上皇(じょうこう)」になる。 |
| 752年 | 東大寺の大仏開眼供養(かいげんくよう)が行われる(大仏の目に魂を入れる儀式)。 |
| 756年 | 聖武天皇が亡くなる(56歳)。遺品は「正倉院(しょうそういん)」に納められる。 |
聖武天皇が大仏をつくった理由
奈良時代(聖武天皇の時代)には、いくつもの大きな災いが日本中をおそっていました。
たとえば、大きな地震や日照り、水不足によるききん(食べ物がとれないこと)、さらに「天然痘(てんねんとう)」という命にかかわる病気が全国に広がり、たくさんの人が亡くなりました。そのうえ、反乱も起きて、国の中は不安でいっぱいでした。
こうした中で、聖武天皇は「この国の人々が安心してくらせるようにしたい」と強く思いました。
そして、そのためには、人々の心をおちつけ、国全体に平和をもたらすものが必要だと考えたのです。
当時、日本では仏教がとても大切にされていて、「仏の力は人々をまもる」と信じられていました。そこで聖武天皇は、「大きな仏さま(大仏)を作り、その力で国を守ってもらおう」と考えました。これが、奈良の「東大寺の大仏」をつくるきっかけです。
743年、聖武天皇は「大仏をつくる」と正式に発表しました。このようにして、大仏は国の平和と人々の幸せを願ってつくられた、当時の人々の希望のしるしだったのです。
聖武天皇が国分寺を建てた理由
聖武天皇の時代、全国に大きな災いがありました。
たとえば、大きな地震が起きたり、ききんや病気で多くの人が亡くなったりしました。さらに、九州では藤原広嗣(ふじわらのひろつぐ)という人物が反乱をおこし、国の中はとても不安定でした。
聖武天皇は、「こんな時こそ、人々の心を一つにし、国をしっかりまとめていかなければならない」と考えました。そして、そのためには仏教の力をかりるのが一番よいと判断しました。なぜなら、仏教は「人々の苦しみをなくす」「平和な心を育てる」という教えだからです。
741年、聖武天皇は「全国の国ごとに国分寺(こくぶんじ)と国分尼寺(こくぶんにじ)を建てなさい」と命じました。
国分寺はお坊さんの寺、国分尼寺は女の修行者(尼さん)の寺です。
これによって、全国の人々が仏さまの教えにふれ、心をおちつけることができるようにしたのです。
また、全国に同じようなお寺をつくることで、「日本は一つの国なんだ」と人々に感じてもらうねらいもありました。つまり、国分寺は心のよりどころであると同時に、国を一つにまとめるための大切なしくみでもあったのです。