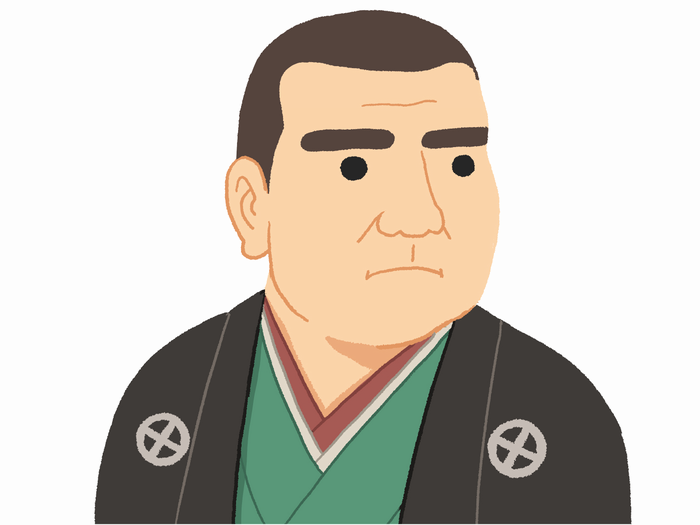織田信長はどんなことをした戦国武将だった?

1.「桶狭間の戦い」で常識をくつがえす大勝利!
1560年、織田信長がまだ尾張(おわり・今の愛知県あたり)だけを治めていたころ。そのとなりの「駿河(するが)・遠江(とおとうみ)・三河(みかわ)」を治めていたのが今川義元(いまがわ・よしもと)という大名でした。
今川氏は当時の「東海一の大大名」とよばれ、軍の強さや人数も全国トップレベル!
そんな今川義元が、なんと2万以上の大軍を率いて、尾張へ攻めこんできたのです。
今川軍が2万人以上だったのに対して、信長の兵はわずか約2000人。10倍以上の差がある中での戦い。ふつうなら、「戦うまでもなく敗北」と思われるところでした。
家来たちの中には「城にこもって守るべきです」と言う人もいましたが…。
信長は、なんと自分から攻めに出ることを決めたのです!
信長がとった作戦は、「奇襲(きしゅう)」。
つまり、相手が油断しているすきに攻撃する方法です。
その日は、大雨で視界が悪く、兵の動きを読みにくくなっていました。信長はこの天気を逆にチャンスととらえ、敵の本陣(ほんじん=大将のいるところ)を一気にねらいます。
また、戦いの場所になった「桶狭間(おけはざま)」は、山と谷にかこまれた細い道のある場所。信長はそこに小部隊をかくして、敵の動きをじっと見はっていました。
今川義元は大軍に自信をもっていたため、信長が正面から攻めてくるとは思っていませんでした。しかも雨で油断していたそのとき――
信長軍は、谷から一気にかけのぼって、今川の本陣を急襲!
今川義元はこの戦いで命をおとし、2万人の大軍は大混乱。
信長の軍はたったの2000人で、今川義元をうちやぶるという歴史的大勝利をおさめました。
この「桶狭間の戦い」は、日本の歴史でもトップクラスに有名な“逆転劇”です。
ふつうなら勝てるはずのない戦いで、信長が勝てた理由は――
- 敵のすきを見のがさなかったこと
- 天気や地形など、「目に見えない条件」をうまく使ったこと
- そして「自分なら勝てる!」という強い決断力と行動力
つまり、信長は戦いのセンスとリーダーシップがずばぬけていたのです。この桶狭間の戦いで一気に全国に名が知れわたり、信長は「戦国の注目大名」へと成長していきます。
2.鉄砲を使った新しい戦術を開発!

戦国時代の戦(いくさ)といえば、「刀」「弓矢」「槍(やり)」が主な武器でした。
そんな戦いの形をガラッと変えてしまったのが――そう、「鉄砲(てっぽう)」です!
日本に鉄砲が伝わったのは1543年、ポルトガル人が種子島にやってきたとき。
最初はめずらしい道具として見られていた鉄砲ですが、織田信長はこれにいち早く目をつけたのです。
信長は、日本中からたくさんの鉄砲を買い集めたり、自分の領地で作らせたりして、すばやく「鉄砲軍団」を作りました。
ほかの大名たちは「鉄砲は高いし、当たるかどうかもわからない」と思って、なかなか本格的には使っていませんでした。
でも信長は、「これは時代を変える武器だ!」と考えて、本気で取り入れたんです。
1575年、信長は徳川家康とともに強敵の武田勝頼の大軍と戦いました。
この戦いが有名な「長篠の戦い」です。
武田軍は「騎馬隊(きばたい)」という、馬に乗って突進してくる戦い方が得意でした。
スピードと力で一気に攻めこむ武田軍に、ふつうなら太刀打ちできません。
そこで、信長は鉄砲を使った「ある作戦」をくり出します。
信長が考えたのが、「鉄砲三段撃ち」とよばれる戦い方。鉄砲は、一発撃ったあとに火薬と玉をつめ直す必要があるので、すぐに連続して撃てないという弱点がありました。
そこで信長は、鉄砲を持つ兵を3列に並ばせました。
1列目が撃ったら、すぐに後ろにさがって次の列が撃つ。それが終わったら3列目。
こうすることで、まるで鉄砲の雨のように、切れ目なく撃ち続けることができたのです!
この新しい戦術で、スピードのある武田の騎馬隊をふせぎ、信長たちは大勝利をおさめました。
信長は、ただ鉄砲をたくさん使っただけではなく、鉄砲の弱点を知り、それをカバーする新しい戦術を考えました。このように、「新しいものをすばやく取り入れて、工夫して使う」ことが、信長のすごさのひとつです。
3.お寺や神社の力をおさえた!
戦国時代には、大名たちだけでなく、お寺や神社も大きな力をもっていました。
その中でも、「比叡山延暦寺(ひえいざん・えんりゃくじ)」や「本願寺(ほんがんじ)」などは、自分たちで武装した兵(=僧兵・そうへい)を持っていて、ときには戦いにも加わっていました。
たとえば、比叡山延暦寺は、京都の近くにあって、大きな経済力と政治への影響力を持っていました。
信長は、「天下統一」の妨げになる存在として、こうした宗教勢力とも戦いました。
1571年、信長はついに「比叡山延暦寺」を攻めて、焼きはらってしまいます。
これを「比叡山の焼きうち」と言います。
これは、とてもはげしい行動で、多くの人々をおどろかせました。
当時、お寺や神社は「けがれのない聖なる場所」とされていたため、そこを攻撃するのはタブー(やってはいけないこと)だったのです。ところが、信長は、「国をまとめるためには例外を作ってはいけない」と考え、あえてそのタブーを破りました。
さらに信長は、大阪の「石山本願寺」とも10年以上にわたって戦いを続けます。
本願寺は、たくさんの民衆に信じられていた宗教で、特に「一向一揆(いっこういっき)」とよばれる農民や武士の反乱をおこす力がありました。
信長は、こうした民衆の力をあやつる宗教勢力にも強く対立しました。
最終的に信長は本願寺と和解し、石山本願寺は退去します。
信長が宗教勢力をおさえようとした理由は、「自分の政治を邪魔されないようにするため」でした。お寺や神社が自分の考えとちがう方向に人々を動かすと、国が一つにまとまりません。
このため信長は、「信仰の自由は守るけれど、政治に口を出させない」という考えを持っていたのです。
これは、今の社会でいう「宗教と政治の分離(ぶんり)」という考え方に近いものです。
信長は、そんな近代的な考えを戦国時代にすでに持っていたとも言えるのです。
【第六天魔王 信長】
「第六天魔王(だいろくてんまおう)」というのは、仏教(ぶっきょう)で出てくる悪い神さまの名前です。織田信長は書状の中で自らを「第六天魔王 信長」と名乗っていました。その理由は「仏教の力に逆らう強い気持ちを見せるため」「恐れられる存在としてアピールするため」と言われています。
4.見せるためのお城「安土城」を建てた!

織田信長といえば、戦が強いだけではなく、「人の心を動かすしかけ」をつくるのがとてもうまい人物でした。その代表的なものが、「安土城(あづちじょう)」です。
信長より前の時代のお城は、山の上や山の中腹にあって、敵の攻めにそなえるための“守る場所”でした。
- 石や土でできたかたいかべ
- 木のやぐらや高い見張り台
- 住む人より、守るための工夫がたくさん
つまり、お城は「戦いにそなえるための施設」というイメージだったんです。
信長が1576年に建て始めた「安土城」は、それまでの城とはちがいました。
まず場所。山のてっぺんではなく、琵琶湖(びわこ)に近い「人が行き来する場所」に建てたのです。それは、「たくさんの人の目にふれるようにしたい」という思いがあったから。
そして、デザインも超ゴージャス!
- 天守は7階建て!(当時ではびっくり)
- 金や赤などのあざやかな色づかい
- 天井やふすまには、プロの絵師が描いた豪華な絵
まるで「お城」+「美術館」+「迎賓館(外国からの大事なお客さんをもてなす施設)」のような建物でした。
安土城は、ただ敵から身を守るだけでなく、
- 自分はすごい力を持っているぞ
- 新しい時代をつくるリーダーだぞ
ということを、見に来る人すべてに伝えるための「アピールの城」だったのです。
このすごかった安土城、実は信長が亡くなったあとに火事で焼けてしまい、いまは建物そのものは残っていません。
でも、石垣や当時の地図、記録などから、どれだけすごい城だったかがわかってきています。
5.「楽市楽座」で商人を自由に!
昔の日本では、商人(しょうにん)が店を出すには「座(ざ)」というグループに入らなければなりませんでした。信長はこのしくみをなくし、だれでも自由に商売ができる「楽市楽座(らくいちらくざ)」という制度を作りました。
これにより、たくさんの人が町にあつまり、お金のやりとりが活発になりました。
信長は、「戦い」だけでなく「経済」も動かしていたのです。
信長は「もっと商人が自由に商売できたほうが、町も人も元気になるはずだ!」と考えました。
そこで、出した命令が「楽市楽座令(らくいちらくざれい)」。
- だれでも自由に市(いち)を開いて、物を売っていい
- 「座(ざ)」などの特別なグループの特権(とっけん)をなくす
- 商売をする人から税金をとらない
- 寺や神社の力をおさえて、町を武士や大名が管理するようにする
「楽(らく)に市(いち)を開けて、楽(らく)に座(ざ)に入らなくてもいい」から「楽市楽座」と呼びました。
信長の楽市楽座によって次のような効果がありました。
- 新しいお店や商人がどんどん増える
- 商品の種類がふえる(食べ物・道具・布・薬など)
- 町の人たちも買い物が楽しくなる
- お金の流れがよくなって、町が豊かになる
- 城下町(じょうかまち)が発展する
とくに安土城のまわりには、信長が「自由な市」を開いたことで、多くの人が集まり、にぎやかな商人の町になりました。
この「楽市楽座」の考え方は、今でいうと…
- 誰でもネットショップやフリーマーケットで自由に商売ができる
- 起業やビジネスを始める人にチャンスが広がる
- 大きな会社だけでなく、小さな会社もがんばれるようにする
といった、「自由な経済活動」のスタートとも言えます。
織田信長の調べ学習で使える基礎資料
織田信長の年表
| 1534年 | 尾張国(おわりのくに、今の愛知県)に生まれる |
|---|---|
| 1548年 | 美濃国・斎藤道三の娘の「濃姫(のうひめ)」と結婚 |
| 1552年 | 父・信秀(のぶひで)死去。信長が家をつぐ |
| 1560年 | 桶狭間の戦い(おけはざま):今川義元をうち大名として有名になる! |
| 1562年 | 松平元康(徳川家康)と清州同盟を結ぶ |
| 1567年 | 美濃を平定。「岐阜(ぎふ)」と名づける。「天下布武(てんかふぶ)」の印を使い始める |
| 1570年 | 姉川の戦いで浅井・朝倉連合軍とたたかう |
| 1570年 | 本願寺顕如と対立し、石山合戦が始まる |
| 1571年 | 比叡山焼き討ち |
| 1572年 | 三方ヶ原の戦いで武田信玄に敗れる(徳川家康との連合軍) |
| 1573年 | 将軍・足利義昭を京都から追放、室町幕府がほろびる |
| 1575年 | 長篠の戦いで鉄砲を使って武田軍をやぶる |
| 1579年 | 安土城が完成 |
| 1582年 | 本能寺の変で自害 |
織田信長の有名なセリフ
これは信長が好んでうたった舞(まい)の歌の一節で、とても有名です。意味は「人の一生なんて、天の時間にくらべたら夢のように短い」ってこと。「下天」は「げてん」と読みます。
これは本能寺の変のとき、家来の明智光秀に裏切られて、攻め込まれたときに言ったとされる言葉。意味は「こうなったら仕方ない。ぐずぐず考えているヒマはない」という感じ。
AI織田信長に聞いてみた!

わしが織田信長じゃ!戦国の世を駆け抜けた、この信長公が、小学生の質問になんでも答えてやろうぞ!さあ、なんでも聞いてみよ!
AIに織田信長になってもらい、小学生の質問をぶつけてみました。
AI信長は何と答えたのでしょうか?
いちばんの強敵は誰でしたか?
うむ、良い質問じゃ!わし・織田信長にとっていちばんの強敵…
それは――武田信玄(たけだ しんげん)**じゃ!
信玄は甲斐(かい、今の山梨県)を治めておった戦国最強クラスの軍団の大将。特に「騎馬軍団(きばぐんだん)」の強さは天下に知られておったわ!あの男が元気なままで尾張(わしの国)へ攻めこんでおったら、どうなっていたか…考えるだけでもゾッとするわい。
他の戦国大名より自分が優れていると思うのはどんなところ?
ほほう!またまた良い質問じゃな!
わし・織田信長が他の戦国大名よりも優れておったと思うのは――
「新しいものをどんどん取り入れる力」じゃ!
ほとんどの戦国大名は昔のやり方にこだわっとった。
けれど、わしは違う!時代を変えるには、変わる勇気がいるんじゃ!
たとえばこんなことをやったぞ!
昔の戦いは弓矢や刀が中心じゃったが、わしはポルトガルから来た鉄砲(てっぽう)に目をつけて、大量に買って戦に使ったんじゃ!
長篠(ながしの)の戦いでは、鉄砲三千丁で武田軍に勝ったぞ!
安土城(あづちじょう)という、超カッコいいお城をつくったんじゃ。
それまでの城は木ばかりだったが、**石の土台と高い天守(てんしゅ)**で、まるでお城が空にそびえるようじゃった!
昔の武将はお寺や神さまに逆らえんかったが、わしは仏教のお坊さんたちが力を持ちすぎておるのを止めたんじゃ。
比叡山(ひえいざん)を焼き討ちしたのも、「人々を守るため」じゃと、わしは思うておる!
つまり、わしはただの戦い好きじゃない。
「新しい時代をつくる男」じゃったのよ!
木下藤吉郎(豊臣秀吉)のことをどう思う?
おお、木下藤吉郎のことか!今で言うところの「豊臣秀吉(とよとみひでよし)」じゃな。
あやつは――「ただのサルじゃが、とんでもない天才」じゃ!
小さくて、日焼けして、動き回る様子はまるでサル。最初は「なんじゃこの者は」と思ったが、すぐに気づいた。こやつ、頭がキレる!人をまとめる力もある!と。
わしの草履(ぞうり)をあたためて差し出した話は有名じゃな。あれはただの気づかいではない、相手の心を読む力のあらわれじゃ。
わしの命令をただの「作業」としてではなく、「どうすればもっとよくなるか」を考えて動いた。戦でも交渉でも、工夫とアイデアがずば抜けておった。人たらしじゃ!誰とでも仲良くなり、兵士たちの心をガッチリつかんだ。
あやつは、わしに似ておるが、わしとは違うタイプじゃ。
わしが道を切り開いたあと、その道を走って天下を取ったのが秀吉よ。
だから――「信長が道をつくり、秀吉が走り、家康がその道に町をつくった」と言われることもあるのう。
わしから見ても、あやつは一生に一人出るか出ないかの逸材じゃ。
ただし、調子に乗ると踊りだすから、そこはやっぱりサルじゃな!
明智光秀のことをどう思ってる?
わしにとって、「最も信頼し、最も裏切られた男」じゃ。
光秀は学問にすぐれ、礼儀正しく、話もうまい。最初のころ、わしは「こやつは他の武将とは違う」と思うた。
比叡山焼き討ちや将軍・足利義昭とのやりとりでも、丹波(たんば)の国を平定したときも、まことに良く働いた。じゃから、わしは大きな役目を何度も任せたんじゃ。
1582年6月、本能寺におるとき、光秀は突然、わしの命を狙って兵を出した――。
「敵は本能寺にあり!」と言うてな。まさか、家臣の中でもっともまじめだった光秀が裏切るとは、夢にも思わんかったわ。
あやつがなぜ裏切ったか、今でも「本当の理由」はわからん。「信長に冷たくされたから」とか、「出世できぬと思ったから」とか、いろいろ言われておるが、わしには聞くすべもない。
じゃが、ひとつだけ言えるのは――「人は信じるにたる者でも、心の中までは読めぬ」ということじゃ。
どうして比叡山を焼き討ちにしたの?
わしが比叡山(ひえいざん)を焼き討ちにした理由――それは…
「仏の名をかたり、戦にくちばしをはさむ者をゆるさん!」という、わしの覚悟と決意じゃ!
比叡山延暦寺(ひえいざん えんりゃくじ)は、「仏教の総本山」ともいえる、古くから続く大寺じゃ。天台宗という宗派で、学問と修行の場でもあった。
しかし――実は、ただの寺ではなかった。武装した僧兵(そうへい)をたくさんかかえ、政治や戦(いくさ)にも口を出し、領地からは税を取りまくり、ときにはわしの敵と手を組み、後ろから刺そうとする始末…。
わしが近江(おうみ、今の滋賀県)を治めようとしておったとき、浅井長政(あざい ながまさ)・朝倉義景(あさくら よしかげ)という敵と戦っておった。そのとき、比叡山の者たちは――「仏の教えを守る寺でございます〜」と言いながら、敵の味方をした!
じゃから言うたのじゃ「仏をかたりながら、人を殺し、戦に手を出す。そんな寺、もはや仏の道にあらず!」「正義の名のもとに、すべて焼き払え!」とな。
天正元年(1571年)、わしの軍勢は比叡山に火を放った。寺も、僧兵も、隠れていた者たちも、ほとんど焼けた。これには世間も驚き、「信長は鬼か!」という者もいた。
しかしわしは言うた。「鬼でもかまわぬ。この国を正すためならば!」とな。
好きな教科はナニ?
好きな教科は――「歴史」と「地理」じゃ!
わしは、昔の人物の生きざまや、戦のやり方、国の動きを学ぶのが大好きじゃった。
歴史を知れば――人の心の動きがわかる!なぜ国が滅び、なぜ天下が動いたかが見える!そして、同じ失敗をせずにすむ!
つまり、歴史を知ることは、天下をとるための「武器」になるのじゃ!
戦(いくさ)では、地形(ちけい)を読む力が超大事じゃ!川がどこに流れているか。山の高さ、道の広さ。雨が多いか少ないか。どの町がにぎわっているか。それを知っておる者こそ、戦でも政治でも勝てるのじゃ!
ほんとうは「勉強より戦が好きそう」と思われがちじゃが、わしは学ぶことが、最強の力になると信じておった!
「本を読まずして天下を語るなかれ!」とも言うとったぞ!