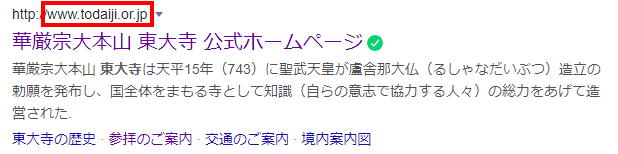わかりやすい地図記号を考える
地図記号は、地図を読みやすくするために使われるマークです。
例えば、丸の中に十字が入った記号は病院を意味しています。
地図の中に「病院」と文字で書くよりマークで書いたほうが目立ってわかりやすくなりますよね。
ただ、この「わかりやすい」ということには落とし穴があります。
温泉マークはわかりやすい?
地図記号は世界共通ではありません。このため日本を訪れた外国人が日本の地図記号を見ても何を表わしているのかわからないことがあります。
例えば、温泉マーク。日本人にとってはわかりやすい温泉マークも、外国人にとってはわかりやすいものではなく、「温かい食べ物がある飲食店」と思ってしまうことがあります。
そこで、外国人にもわかりやすい温泉マークが考案されました。人が温泉に入っているのがイラスト化されていますね。
| 通常の温泉マーク | 外国人にもわかりやすい温泉マーク |
|---|---|
 |
 |
このように外国人観光客が増えていることから外国人にもわかりやすい地図記号の検討が始まっています。ほかにどのようなものがあるか国土地理院のサイトに表示されています。下記から見ることができるので、どんなものが考えられているかチェックしてみてください。
⇒ 外国人にわかりやすい地図表現検討会
地図記号を日本と外国で比較
郵便局のマークも日本と外国ではちがいます。
日本での郵便局の地図記号はカタカナの「テ」を丸で囲んでデザイン化したものです。むかし、郵便を扱っているところが逓信省(テイシンショウ)といったため、このマークになりました。
ただ、逓信省(テイシンショウ)の「テ」というのは、日本独自のものなので、外国では用いられていません。外国では封書をデザインしたマークが郵便局のマークとしてつかわれています。
日本と外国で地図記号がちがうものは他にもたくさんあります。交番も日本は「×」に丸がついたマークですが、アメリカの地図では「Police Station」と文字で書かれていたり、パトカーの絵が描かれています。
こんなの知ってる?めずらしい地図記号
昔はなかった施設については新しい地図記号が考えられています。
例えば、次のような場所にも地図記号があります。
| コワーキングスペース | 自営業の人やリモートワークをする人が利用する仕事場 |
|---|---|
| スマートフォンの充電スポット | スマートフォンを充電できる場所 |
| シェアサイクルステーション | 街中で使う自転車を借りたり返したりする場所 |
| EV充電スタンド | 電気自動車を充電する場所 |
| ATM | お金を引き出したり預けたりする機械 |
新しいマークはコンビニを表わすのにサンドイッチと飲み物の絵が使われているなど外国の人が見てもわかりやすいように工夫されています。
地図記号を覚えておくと災害時に役に立つ!
何のために地図記号なんか勉強しなけやイケないの?と思うかもしれませんが、地図記号を覚えておくと大地震などの災害時に役に立つからです。
例えば、大きな地震や台風のとき、どこに避難するか、けがをしたらどこで治療を受けられるかをすばやく見つけるために地図記号が使われます。
災害はいつ起こるかわかりませんが、地図記号を知っていれば、いざというときに頼りになります。
避難場所や病院、消防署、警察署などの地図記号は、普段から確認しておくと安心です。
また、公衆電話や水道施設の場所も知っておくと、災害時に困りません。
地図を開いて、自分の周りにどんな地図記号があるか探してみましょう。
小学生向け地図記号の覚え方
覚えやすいように地図記号とイラストを一覧形式にしました。目で見て覚えましょう。イラストで見ると「あの部分」が地図記号になったんだなということがよくわかります。
クリックすると(↓)、何の地図記号かイラストの下に文字が表示されます。
郵便局、小中学校、高等学校、警察署、図書館、神社、市役所、消防署、老人ホーム、博物館、病院、発電所等、灯台、温泉、裁判所、保健所、畑、田、交番、税務署、風車、漁港、広葉樹林、針葉樹林
地図記号ってなに?
地図記号とは、地図上で場所や建物の種類をわかりやすく示すためのマークです。例えば、「学校」や「病院」など、私たちがよく行く場所が地図に小さなマークとして表されているのを見たことがありますよね。これが地図記号です!
地図記号の覚え方のコツ
地図記号を覚えるコツは、「形の意味や由来を知る」ことと、「実際に地図を使ってみる」ことです。
例えば、郵便局の記号は郵便を意味する「〒」のマークそのままなので、実際に郵便局で見たことがある人も多いでしょう。
郵便局を管轄している省庁を昔は「逓信省(テイシンショウ)」といいました。この「テ」から現在の郵便マークが誕生しました。
主な地図記号の意味
こちらはよく見かける地図記号とその意味です。これぐらいは覚えておきましょう!
| 病院 | 赤十字のマークから |
|---|---|
| 警察署、交番 | ×は交差した警棒を表している |
| 神社 | 鳥居のカタチ |
| 図書館 | 開いた本のカタチ |
| 消防署 | 江戸時代に火消しに用いた「さすまた」のカタチ |
| 裁判所 | 裁判の内容を市民に知らせるために使っていた立て札のカタチ |
| 税務署 | 計算をするために用いた「そろばん」のカタチ |
| 郵便局 | 「逓信省(テイシンショウ)」の「テ」から |
もし、新しい地図記号を作るとしたら、どんな記号を作る?例えば、秘密基地を表す記号とか、大好きな公園の特別な遊び場を表す記号とか、自由に考えてみよう!
地図記号を作る時のポイントは、次の3つ。
- 誰が見てもわかりやすいこと: 「これは何だろう?」と迷わないように、見ただけで意味が伝わる記号が良いね。
- シンプルであること: 複雑すぎると、書くのも見るのも大変になっちゃうから、できるだけシンプルな形が良いよ。
- 他の記号と間違えにくいこと: 似たような記号があると、混乱してしまうから、他の記号とは違う特徴的な形にしよう。
自分が作った地図記号を使って、友達と「ひみつの地図」を作ってみるのも楽しいよ!地図記号は、ただ覚えるだけじゃなくて、自分で作ってみることで、もっともっと地図の面白さがわかるようになるんだ。
国土地理院のサイトにある地図記号
地図記号の一覧表は国土地理院の子ども向けページにあるものがよくまとまっています。PDF形式のファイルなので必要に応じて印刷することもできます。
国土地理院 > 子どものページ > 地図記号
このページにある地図記号シート表示で一覧形式のものが表示されます。

また、新しくできた地図記号も知ることができます。
- 博物館
- 図書館
- 老人ホーム
- 風車
- 電子基準点
これらが新しくできたものです。
身近な場所なのに「公園」には決まった地図記号がありません。理由は、「公園」には色々な種類があるからです。たとえば、小さな遊び場から大きなスポーツ施設まで、公園の形や使い方がちがいます。そのため、すべての公園を1つの記号で表すことがむずかしいので決まっていないのです。
地図記号の勉強ができるゲーム
最後に地図記号の勉強ができるサイトを紹介したいと思います。
神経衰弱ゲームで、名称とマークをあわせるものです。
毎回、カードの場所は変わるので何回も挑戦してみてください。
⇒ 地図記号の神経衰弱ゲーム